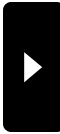2022年02月05日
東風と書いてはるかぜ
立春を過ぎましたが
気温はまだまだ低く
思わず「さむい!」と言ってますね
しかしながら
麦の成長や自然を感じると
少しずつ春を感じます

立春から啓蟄までの間に
春一番の南風が吹きます
七十二候では、「東風」をはるかぜ
と呼びます
春は陰陽五行で東を司るために
春の風を総称しているようです
そして、
草木の凍てつきがほどける瞬間の
わずかな気配を風で表現するそうです
梅の香りを運ぶ「梅東風(うめごち)」
椿が咲く日の「椿東風(つばきごち)」
などなど
自然を言葉で表現し
後世に伝えている「和の言葉」
とても美しく心にしみます
日本とは何か?
自然を愛し、大事にする心
ですね
2022年02月04日
炭山の棚田歩き教室とは
二千年以上続く
日本独自の健康法
日本独自の健康法
日本では、糖尿病、がん、肥満、
認知症といった現代病が
増え続けています。
増え続けています。
何故、この様な不健康な体に
なったのだろうか?
その謎を「炭山の棚田歩き」教室で
紐解きます。
そして、
日本人に合った健康づくりが
みつかります
日本人が忘れている
決してなくしてはいけない宝を
一緒に取り戻しましょう
詳しい内容は、
下記の専用ページから
ご確認ください。
ご確認ください。
炭山の棚田歩き教室は
こちらです

2022年02月03日
危機が迫ると行動する
慶応年間の1865年から1867年に
佐賀県伊万里市二里町周辺で
大飢饉が発生
ちょうど幕末、
大政奉還があった頃の話です
その時に立ち上がったのが
地元の酒造業4代目
吉永 伊兵衛で当時30歳そこそこだったと
吉永伊兵衛は、巨財を投じて
開墾が困難な地域に事業を起こし
見事に水田をつくり民を救済した
これを「極難開(ごくなんびらき)」と呼び
当時に造られたであろう石積みが残っています

その石積みの田んぼから眺める景色

150年前の人も同じような景色を
見ていたとすれば、今の世の中を
どう感じるだろうか・・・
大型の機械もない時代に
人々が助け合い、食べるために
荒れ地を開墾し、見事に成就させる
こんな先人達の思いが詰まった場所を
私たちは決してなくしてはいけない
ある意味
今の世の中も危機的な状況
危機が迫り行動する人、
何もしない人、
歴史から学んでいきましょう
今回登場した場所は、
佐賀県伊万里市二里町の
「炭山の棚田」です
引用文献は、「二里町史」
編纂に関わったすべての方に
感謝申し上げます
2022年01月27日
60歳を過ぎてからの米づくり
定年後、もしくは60歳を過ぎて
一から米づくりを始める
そんなことを考えたり
実際に米づくりを始める人は
どのぐらいいるだろうか?
令和3年の統計では、
佐賀県内の新規就農者は
160人、米や麦づくりに就農した数は
30人と2割程度、、、
さらに、160人の新規就農者の中で
60歳以上はたった一人です
平成28年までさかのぼっても
5年で25名という現実、、、
これでは、田んぼが荒れていくわけです
そこで、一計を案じました
新規就農という方法で
米づくりの人口を増やすのではなく
健康づくりの一環として行う
それが「棚田で健康学校」です
田んぼの荒廃を防ぎ、
あなたの身にも起こる可能性がある
がん、糖尿病、認知症といった健康不安を
解消していく
そして、人生の生きがいを見つけ
残りの人生を米づくりという日本の
伝統技能をつなぐ守り人になる
いかがですか?
その「棚田で健康学校」を
3月から開講します
まずは、3月5日(土)午前中に
説明も兼ねた「棚田歩き」教室を行います
場所は、
二里町の「炭山の棚田」です
詳しい内容は、
2月4日(金)に公開致します
雄大な炭山の棚田からの光景、
三世代が織り成す空間、
一緒に未来の子どもたちから贈られる
宝ものを受け取りましょう

2022年01月24日
平戸街道を行く
週末の山走り
田んぼの近くには
菜の花が咲いていました

そして、
いつの間にか平戸街道の看板が・・・
一つ目 ↓

二つ目 ↓

子どもの頃から「お地蔵さん」の
愛称で地元の人に親しまれています

私も必ず行きかえりに立ち寄って
手を合わせています
最後の一つは
隠れた絶景スポット
殿様もこの光景を
目にしていたんでしょうね

江戸時代は田畑の開墾が
盛んだったので今とは景色も
違ったでしょうが海や空は当時のまま、、、
この看板を設置された有志の方々
ありがとございます。
タグ :平戸街道
2022年01月22日
棚田歩き ~炭山の棚田~
大寒の日に棚田歩き
歩いていると足元に小さな

今回歩いた棚田は、
そんな石積みの棚田から眺める景色が
そして、

標高260mのこの場所から

今回、棚田歩きのコースを実際に歩き
歩いていると足元に小さな
花を発見、、、
調べると「すみれ」ではないかと
こんな寒い時期に小さくも
調べると「すみれ」ではないかと
こんな寒い時期に小さくも
可憐な花が咲いていると心がほっこりしますね

今回歩いた棚田は、
伊万里市二里町の「炭山の棚田」
棚田で健康学校で行う「棚田歩き」
出発地点から最後まで歩いての距離や
傾斜、景観、花、草、鳥といったことを確認しました
下の写真は、昨年まで見ることができなかった
下の写真は、昨年まで見ることができなかった
棚田の石積みです

すみやま棚田守る会の木寺会長や

すみやま棚田守る会の木寺会長や
棚田を守る人達が、新年早々に竹や木を伐採し
草払いをされたそうです
そんな石積みの棚田から眺める景色が
下の写真です

椨(タブノキ)展望所から眺める景観も

椨(タブノキ)展望所から眺める景観も
素晴らしいですが、横から棚田を見るのも
絶景です
そして、
今回の最終目的地へ行く前に歩いた場所が
下の写真です


道の左右には日本の山に多く見かける
杉やヒノキではなく、どんぐりの木が
杉やヒノキではなく、どんぐりの木が
生い茂っています
そして、鳥のさえずり、
木々の香り、木漏れ日と
癒やしの空間です
最後に足を運んだのが
国見炭鉱の跡地

標高260mのこの場所から
当時の国鉄 夫婦石駅(めおといし)まで
ケーブルを使って石炭を運んでいたとか、、、

今回、棚田歩きのコースを実際に歩き
新しい発見や感動もありました
この発見や感動を一人でも多くの方に
知っていただけるようにと
知っていただけるようにと
3月5日(土)
二十四節気の「啓蟄」に
体験イベントを開催いたします
詳細は、2月4日(金)
立春の日にお知らせいします
お楽しみに、、、
2022年01月16日
なぜ農業をする人が増えないのか?
今の農業について調べると
どうしても「生産性」を高めることが
重視されています
日本は国土が狭く、平地も少ないため
人の生産性を高めるのに向いていません
例えば棚田です

しかし、国の政策を見ると「人」
の生産性を高めることが多ように感じます
圃場整備による水田や畑の面積拡大、
機械化、スマート農業といった
大規模農業化です
大規模にすることで人の生産性は
向上しますが、多額の資金が
必要になります
長く続ければ資金は回収できる
かもしれませんが、かならず
追加資金が必要になります
なぜなら世の中の仕組みが
資本主義による経済成長が前提

どうしても「生産性」を高めることが
重視されています
日本は国土が狭く、平地も少ないため
人の生産性を高めるのに向いていません
例えば棚田です

しかし、国の政策を見ると「人」
の生産性を高めることが多ように感じます
圃場整備による水田や畑の面積拡大、
機械化、スマート農業といった
大規模農業化です
大規模にすることで人の生産性は
向上しますが、多額の資金が
必要になります
長く続ければ資金は回収できる
かもしれませんが、かならず
追加資金が必要になります
なぜなら世の中の仕組みが
資本主義による経済成長が前提
になっているからです
そのため、資本力が大きい人が
成長する仕組みになっています
話は大規模農業に戻しますが、
水田、畑作でつくる野菜や穀物は
大規模農業化で人生産性は
向上しますが、
食料生産性は低下します
食料生産性が低下する理由は2つ
1.害虫、冷害の被害
2.売れ残りといった供給リスク
この二つです
逆に家族農業は、多種栽培のため
害虫や冷害の被害も最小限になります
そして、作った分だけを売る
という方法で行えば、
売れ残りリスクもありません
今は、インターネットも活用すれば
特定のお客さんに向けて
予約販売も可能です
しかし、売ることに力を注がない限りは
つくっても売れず、やがて所得を得ることが
難しくなります
ただし、食べる分には困りません
そこで私が考えたのが
これから先、農業従事者を増やす方法は
たった一つ、
「農業で所得を生み出す」という考えから
「農のある暮らしで健康になる」
という考えです
そのため、資本力が大きい人が
成長する仕組みになっています
話は大規模農業に戻しますが、
水田、畑作でつくる野菜や穀物は
大規模農業化で人生産性は
向上しますが、
食料生産性は低下します
食料生産性が低下する理由は2つ
1.害虫、冷害の被害
2.売れ残りといった供給リスク
この二つです
逆に家族農業は、多種栽培のため
害虫や冷害の被害も最小限になります
そして、作った分だけを売る
という方法で行えば、
売れ残りリスクもありません
今は、インターネットも活用すれば
特定のお客さんに向けて
予約販売も可能です
しかし、売ることに力を注がない限りは
つくっても売れず、やがて所得を得ることが
難しくなります
ただし、食べる分には困りません
そこで私が考えたのが
これから先、農業従事者を増やす方法は
たった一つ、
「農業で所得を生み出す」という考えから
「農のある暮らしで健康になる」
という考えです
その実践が春から取り組む
「棚田で健康学校」です
その舞台となるのこ写真の場所です
炭山の棚田 椨展望 ↓

どんな教室なのかは決まり
募集に向けての準備中です
2月4日(金)立春の日に
詳しい内容をご案内いたします
お楽しみに、、、
2022年01月09日
蕨野(わらびの)の棚田を駆ける
菜の花ですかね?
寒咲花菜、冬に咲く菜の花

菜の花が咲いていたのは、
唐津市相知町にある
「蕨野の棚田」

大平展望所からの眺め

こちらの直売所を出発点にして
蕨野の棚田をぐるっと一周
駆け巡りました


スタート地点の標高が約150m
展望所付近で420m程度
距離にして11㎞ですが
長く感じませんね
1月と2月は、
佐賀県内の棚田を駆け巡ろうかと
見かけたときは声をかけてくださいね
2022年01月02日
棚田から初日の出
元旦は寒かったですね
その分初日の出は
絶景でした

空気も澄みきっていて
天山、作礼山、浮嶽といった山並みも
くっきり見えました

初日の出は氷点下4℃の「炭山の棚田」

令和四年、よか一年になりそうです(^^)
その分初日の出は
絶景でした

空気も澄みきっていて
天山、作礼山、浮嶽といった山並みも
くっきり見えました

初日の出は氷点下4℃の「炭山の棚田」

令和四年、よか一年になりそうです(^^)
2021年11月28日
多久トレイルラン2021
棚田でトレイルラン
棚田に足を運ぶたびに感じるのが
トレイルラン(山走り)の
練習場所として最高だということ
坂道、畦道、景色が最高です
炭山の棚田でも何度か練習しました
そして、
11月28日(日)は、
多久トレイルラン2021大会に参加し、
三年越しに完走しました

棚田がトレイルランの
練習場所になり、合宿にも
使えるのではないか?
棚田に住んでいないからこそ
逆に感じることもあります
棚田という遺産は、
またまだ知らない魅力が
たくさんありそうです
足腰に自信があるなら
ぜひ、棚田に足を運んで
走って下さいね
それでは
最後まで読んで頂き
ありがとうございました
棚田に足を運ぶたびに感じるのが
トレイルラン(山走り)の
練習場所として最高だということ
坂道、畦道、景色が最高です
炭山の棚田でも何度か練習しました
そして、
11月28日(日)は、
多久トレイルラン2021大会に参加し、
三年越しに完走しました

棚田がトレイルランの
練習場所になり、合宿にも
使えるのではないか?
棚田に住んでいないからこそ
逆に感じることもあります
棚田という遺産は、
またまだ知らない魅力が
たくさんありそうです
足腰に自信があるなら
ぜひ、棚田に足を運んで
走って下さいね
それでは
最後まで読んで頂き
ありがとうございました