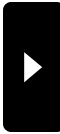2022年02月25日
普通は食べない水菜の花
なんか水菜がいつもと違う・・・
よーく見ると
水菜の先っぽに花のつぼみ?

調べると
水菜の花は食べれるようです
しかも美味だとか
ほうほう
もうしばらく様子見て
花が咲いたら収穫して
たべてみようかと
楽しみが
また一つ増えました

2022年02月24日
最後の里芋
実家の畑で掘った里芋
まずはスコップでざっくり掘り
最後は、遺跡の発掘ぽく周りから
じっくり手で掘り起こしてみました

今年は、これで最後の
里芋掘り
今年は、実家の畑でもう少し
野菜を育てようと計画中です

そして、米づくりは炭山の棚田
できる範囲で昔の日本人が
普通にやっていた農のある暮らしに
帰ろうかと・・・
2022年02月20日
青じその種採り
立春が過ぎ二十四節気の
雨水ですが、今日は雪が舞いましたね
まだまだ寒い日が続くため
畑に出ないで自宅で資料作成が
多い日が続いています
ですが、江戸時代に貝原益軒がまとめた
健康づくりの心得書「養生訓」には
「動かないことは体の血の巡りを悪くする
よって、常に動くこと」と書かれています
そこで、昨年から自宅の
ほったらかし農園でずっと
ほったらかして乾燥している
青じその種採りをしました

種が付いたのを取って
手で揉みほぐして種を取り出します

取り出した種をジップロックに入れて
暖かくなる5月頃に種をまきます

青じそは薬味や炒め物にも使えます
我が家では青じその天ぷらが人気です
今年は、育てた野菜は
すべて種採りまでやって
自然の命をつないでいこうと思います
2022年02月16日
ブロッコリー物語 ~はじまり~
昨年の10月頃に植えたような・・・
ブロッコリー
本来なら昨年末頃には
収穫できるはずなんですが
我が家のほったらかし農園は
その名のごとく「ほったらかし」です
肥料一切なし、
寒さよけ一切なし
その結果、寒い冬を越しました(-_-;)
そして、今週から気温が少し上がり
生育環境に近づいたのでしょうか?
よーく見ると
小さいですが
ブロッコリー発見です⬇

まだ食べられる大きさ?
ではないので
引き続き観察します
それにしても、
ゆ~くり育ってますね
冬を越したブロッコリーは
果たして甘いのか?
それとも・・・
ブロッコリー物語は続く
2022年02月09日
春野菜の準備
昨年末に親父からもらった
スナップえんどうの苗
ゆ~くり育ってます

昨年も
ほったらかして成長したので
今年も大丈夫かと・・・
自宅のほったらかし農園は
そんなに広くないため
季節によって何を育てるか悩みます
今年は、実家の畑で
もう少し野菜を育てようかと計画中
そして、春から開講する
棚田で健康学校でも
一緒に野菜づくりを行います
もちろん米づくりも一緒に
できることから始めます
立春も過ぎて春野菜の準備が
始まりますが季節に合わせて
暮らすことは、健康にもきっと良いことだと、、、
棚田で健康学校の第一回イベント
「炭山の棚田歩き」教室は
3月5日(土)に開催します
あと2名ほど参加できますので
棚田や米づくり、健康に興味関心のある方は
ご参加お待ちしています
詳しくはこちら↓
2022年02月08日
畑から直送の野菜で鍋をつつく
日曜は天気が良ければ
畑で野菜を収穫したり
土いじりです
といっても今は実家の親父が
作っているのを収穫します

サニーレタス、ねぎ
春菊を収穫して
夕食の鍋料理で頂きました
そして、ヤーコンです

ヤーコンは
翌日の弁当のおかずで登場!
美味いですね
こんな感じで
畑でとれた野菜をすぐ食べたり
翌日に食べると食習慣が変わります
加工食品を食べる機会が減り
体にとても良いことです
しかしながら畑もなければ
そもそも野菜を作ろうという考えないのが
普通かもしれません
ただ
トンガの海底火山噴火や
台湾有事なども考えれば
ここ数年の間に食糧難がやってきそうです
平成の米騒動という歴史に学び
今からでも家庭菜園始めましょう
2022年02月07日
戦後の食糧
戦後の昭和22年に
アメリカGHQが指示して
行われた国民栄養調査
その調査内容にも出てくる
アメリカGHQが指示して
行われた国民栄養調査
その調査内容にも出てくる
いも類の「里芋」

今は記載されていません
他にも馬鈴薯という食品があり
馬鈴薯ってのは何?
よく考えてみれば分かりますね
じゃがいもです
たんぱく質の主役は
大豆や獣肉
今の食を見ると
変わりすぎですね

今は記載されていません
他にも馬鈴薯という食品があり
馬鈴薯ってのは何?
よく考えてみれば分かりますね
じゃがいもです
たんぱく質の主役は
大豆や獣肉
今の食を見ると
変わりすぎですね
2022年02月02日
コロナよりも怖いのは・・・
かれこれ2年間
コロナの話題で持ちきりですね
正直ですね出始めの頃は
感染した瞬間に倒れて死ぬかも。。
なんて恐怖心が有りました
今は、恐怖心はありません
理由は2つ
感染症の定義や
PCR検査の不確実性
を知っているからです
正直なところ、いつまで続くんかね~
という感覚です
2つ目は、
人間は、コロナの前から
ウィルスや細菌と共生してきたわけです
大根を掘った時の土の中にも
土壌細菌がウヨウヨいるわけです

人間の体の中にも
100兆個の細菌がいます
そんな細菌やウィルスと共生し
人間の体ができあがってるわけですね
実際に、土の中にいる
土壌細菌には、ストレスを和らげるような
働きをする細菌も存在するようです
ウィルスに関しても
ワクチン1本、2本、3本と
接種したら根絶するわけではありません
100兆個の細菌や
複雑な仕組みで生きてきた人間が
たった1本の注射でウィルスから
身を守れるのかどうか?
よく考えれば分かることかもしれません
コロナより怖いのは、
今やってることが
5年後、10年後と
子どもたちが大きくなった時の
社会の常識になること
2022年01月29日
初体験の麦ふみ
昨年の12月に小麦と
六条大麦をまきましたが
順調?に育っています
写真は小麦です

でもって
踏みました

麦ふみってやつですね
農業全書にも麦ふみについて
書かれていましたので紹介します
同じく中うちの事、
一二寸針生ひの時、
早かるき鍬にて浅く一遍うつべし。
麦の中うちのことですが
針のような芽が1、2寸出てきたとき
まずは軽い鍬(くわ)で浅く軽く
一度中うちをします。
写真の小麦は
少し大きいかもしれませんね(-_-;)
続きです。
これを馬耳鏃(はにぞく)と云ふ。
苗のわづかに生ひ出づる時、
ちいさき矢の根のごとくなる鍬、
又は熊手の類にてうつによりてかくは云ふなり。
鏃の字は矢じりとよむ、細き鍬の類と見えたり。
これを、馬耳鏃(はにぞく)と言い
苗の芽が少しだけ出始めたときに、
ヤジリのような形の小さい刃の付いた鍬や
熊手で中うちをするのでこの様に言います。
んー
江戸時代は鍬で
麦をつぶす?感じでしょうかね
この後、春までに何度も
麦ふみをするらしいですが
昔百姓していた84歳になるお客さんに
麦ふみの話をすると
子供の仕事やったね~と
しみじみと話されていました
ということで、今日の昼から
子どもたちと麦ふみやります
子どもたちの反応が楽しみです
2022年01月26日
自然に生かされている
自宅の小さな畑で育つ
麦や野菜を見ると癒やされます
子どもたちからは畑の親父
なんてことも言われたり・・・

麦も青梗菜も
化学肥料を施さずに育てていますが
太陽の光、気温、水といった
自然の力で育ちます
もっと正確には細菌も関係していますが。。。

ただ、
食べれるまでに大きくしたい!
たくさん収穫したい!
と思えば人が手を加えることも必要
手を加える
というよりも自然循環の
妨げにならないようにする
というほうが正しいかもしれません
昨年の春から野菜づくりを
はじめましたが
化学肥料を与えなくても
なんとか食べれるまで成長するものです
そんな野菜を食べて人は生きるための
栄養素を得ているわけです
そう考えると
人は自然に生かされている
「自然の分け命」
ということですね
今の世の騒動を見渡すと
自然に生かされていることを
忘れたんでしょうかね?
自然に向き合いましょう